品質トラブルを起こすと大変だということはわかったと思います。
(4.1 標準仕様書と特記仕様書を読んでない方はそちらからどうぞ)

設計図と異なれば『品質トラブル』?
設計図に記された通り『そのまま』造ることができたら完璧ですよね。
・・・でも本当にその通りできますか?
少しでも設計図と異なると『品質トラブル』になるのでしょうか?
図面で書かれたことが全て現地で具現化できるかと言われると相当難しい問題があります。
建設業は現地一品生産と言われるだけあって現場ならではの課題があったり
現地にあるものに合わせてモノを作らないといけなかったりします。
そういったときはどうしても設計図通りにはできないことがあるのです。
それは全てが品質トラブルなのでしょうか?
いやそれは違います。
モノをつくる上で定められた『ルール』があるのです。
モノを作る上でのルール
標準仕様書や特記仕様書には品質管理の記載が必ずなされています。
出来形管理基準・品質管理基準なるものです。
出来形というのは図面から構造物を造るときの大きさや形状などを指します。
出来形管理というのはつまり、図面通りのカタチでモノを造りましょうってことを書いています。
品質というのは構造物を造る上でそのモノの構成する要素を指します。
例えば、アスファルト舗装であればアスファルトだし、
コンクリート構造物であれば、鉄筋やコンクリート等を指します。
品質には必ずバラツキがあると言われています。
詳しくは改めて話しますが、例えばコンクリートは複数の素材からできていますが、
必ずしも全く同じ水と砂と石とセメントが混じっているかと言われると産地が違ったり、
セメントにも種類があったりと、いろんなパターン・組み合わせがあり必ずしも同じものではありません。
ですからその性状によっては収縮しやすかったり、膨張したり、
水が多く浮いてきたりします。
そんな中で目的物を造るわけですから、
やはり出来形・品質には多少の誤差が発生します。
バラツキを理解する
これがいわゆるバラツキというものです。
多かれ少なかれ必ずこれはあります。
「基準」が±0というものはありません。
許容できる幅が大きいものは設計値以上と書かれていたり
許容できる幅が小さいものは±5mm等と記載されています。
これはその基準に当てはまっていれば、構造として問題ないですよ。
という判断基準にあたります。
さらに品質でいうと想像できるかと思いますが
コンクリートの柔らかさ(スランプ)は
一般的なものであれば±2.5cmと決められています。
これに倣っておけばそれほどおかしな性状になっていないというものです。
(水が多すぎたり、打込みに問題があるほど硬くなったりしていないということです)
それらの基準を知らずして
とにかくいいものを造ると意気込んでも
品質にはバラツキがあるので、必ず完璧にはなりえないわけですから
ある程度の許容が必要と認識しておく必要があります。
品質トラブルは故意でも故意でなくてもダメなものはダメ
しかし、いいもの造ると意気込んでいるうちはまだいいのですが
逆に基準を知らずして現場管理をするとどうなるでしょうか?
『なんとなくいい感じのものができたが、
本当にこれでいいのかまではわからない。』
という状態だと思いますので、判断ができません。
もしかしたら自分はOKと思っていても、本当はNGで
それがずっと先に気づくことになったり、
発注者に指摘され信頼を失ったりすることにも繋がりかねません。
それがいわゆる品質トラブルというものです。
また、これを読んでくださる方にはいないと思いますが
その問題を知っていたけどあえて
黙っておく・隠す・放っておくという選択をする場合もあります。
めんどくさい・バレなければよい・もう時間が、お金がない
なんてことから基準を超過していても
直さないなんて選択をすることがあります。
それがいわゆる故意の品質トラブルです。
いずれにしても品質トラブルはあってはなりません。
故意であっても故意ではなくても、
工事を担当する以上はプロとして
高い技術レベルを要しておく必要がありますので
基準となる値を頭にいれ、確実にそれを現場で管理しましょう。
どうしても、その基準が判らない場合には
人に聞く、発注者に確認する、そして目標値を定める。
あやふやな状態でモノを作らない!
こうしてより良いものを造る、
決して「こんなもんでいいだろう」という
ものを造るということがないようにしていきたいですね!

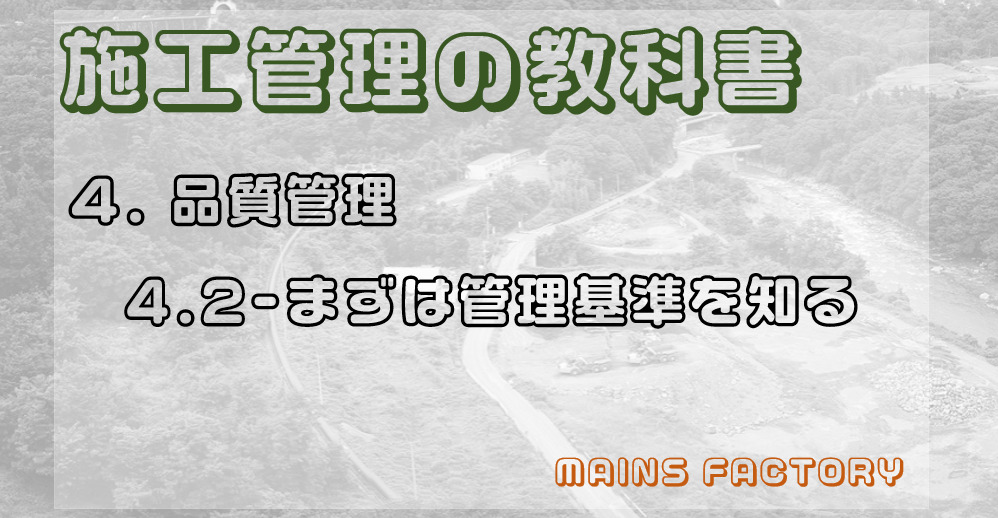


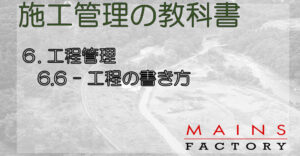
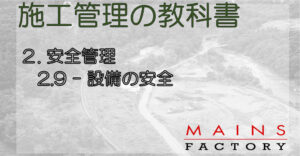
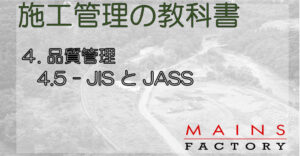

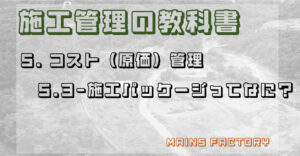
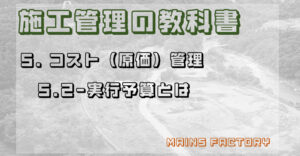
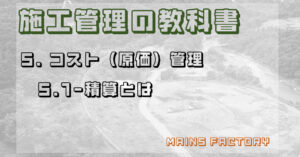
コメント