前章までに建設業に関わるような環境問題をピックアップし御伝えしました。
今回はゼネコンと環境の付き合い方についてお話したいと思います。
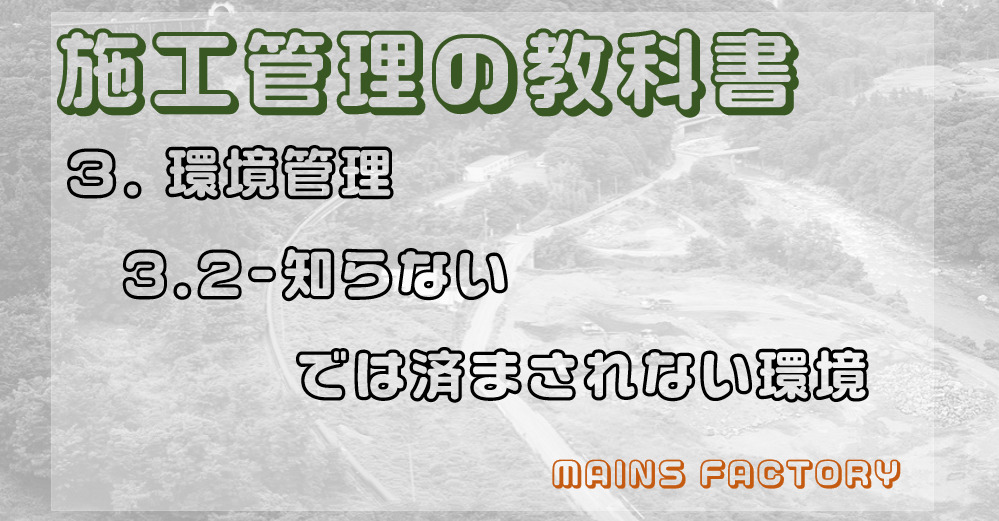
ゼネコンを2側面から考えてみる
ゼネコンといっても非常に広義なので今回はゼネコンを
それぞれの視点から見てみたいと思います
現場と環境の付き合い
現場での環境との付き合いは前章までにお伝えしたように現場を運営する上で,数多くの関係環境法律・法令をそれぞれ満足するように・破らないように仕事するというのが重要になります。
どちらかというと『マイナス要因』にならないように取り組むのが現場での環境との付き合いになります。
濁水排出の例
例えば,とても濁った水が現場で発生した際に,
その水を自治体で定められる許容値内で排水する場合と
ミネラルウォーター並みの清水で排出する場合に
評価が変わるでしょうか?
当然,きれいな方が良いですが
残念ながらその行為による価値は評価されません。
近隣住民と振動の例
逆の話としまして
現場の近隣に住民さんがおられたとします。
法律で定められる振動値よりは小さいが住民さんは揺れて生活できない。
と言ってこられたとします。
そうすれば,より小さな振動になるような施工方法に切り替える必要があったり,
振動が伝播しないような対策を整えたりする必要があります。
当然,これらは事前に判断し,振動の小さい工法を採用するのが本筋です。
しかしその工法を採用しても住民さんから褒めてもらうことはあまり無いと思います。
それは通常時と比べて,さらに振動がなくなるものではないからです。
現場と環境の関係
このように現場での環境対策というのは,多くが『マイナス要因』を取り除くものです。
前章でもお伝えした通り,
ひとたび大きな環境事故を起こすと会社イメージにも影響があり,
最悪,倒産や多額の賠償を行う可能性がありますが,
全てにおいて『マイナス要因』を除去するものでしかありません。
会社と環境の付き合い
次に会社と環境の付き合いです。
近年,環境活動に取り組んでいることをアピールする会社が非常に増えています。
会社のホームページを見れば,
多くに環境への取り組み内容を書いております。(具体的か抽象的かはさておき‥)
つまり会社で行う環境対策は『プラス要因』となるものです。
カーボンニュートラル
それはなぜかと言いますと2050年までに脱炭素化,つ
まりCo2の排出を『実質ゼロ』にするということを日本として表明しているため,
その取り組みの一環なのです。
実際,Co2を出さないというのは人が生活したり,
生産活動を行ったりする上では不可能ですが,
実質ゼロ,つまり吸収したり,Co2を分解したりすることで対応するのがこの取り組みです。
会社と環境の関係
もちろんゼネコンにおいてもこの取り組みは例外ではありません。
そもそもゼネコンとは,
大型重機を用いて,大量にCo2を発生させるセメントを用いて
コンクリートでモノを造るような会社ですから,
社会的にはカーボンニュートラルの逆を行っているわけです。
とはいえ,その活動を辞めると生活が成り立たなくなりますから,
会社としては,施工以外の部分で多くの脱炭素化を行っています。
ゼネコンが行う脱炭素化
ゼネコンが行う脱炭素化への取り組みの例として
・重機,車両のハイブリット化,バイオディーゼル等の代替燃料使用
・重機,車両の排気ガスの改善,燃料から電力使用への移行
・低炭素資材の使用や開発
・再生エネルギーの積極的な使用
等が挙げられます。
逆にこういった取り組みをしなければ環境に配慮していないものとして社会から認められなくなります。
ゼネコンと環境(まとめ)
このようにゼネコンは
現場で行う環境対策は主に『マイナス要因』の排除
会社で行う環境対策は主に『プラス要因』の構築
になります。
当然,会社で決定した『プラス要因』の具体的行動内容は
現場で実践してこそのものも多くありますから
無縁とは言い切れませんがこのような関係がある,
程度には認識しても良いのではないでしょうか。
これからゼネコンにとっても
環境は切っても切り離せない関係になりますので,
私には無関係,とならずにアンテナを張っていきましょう!


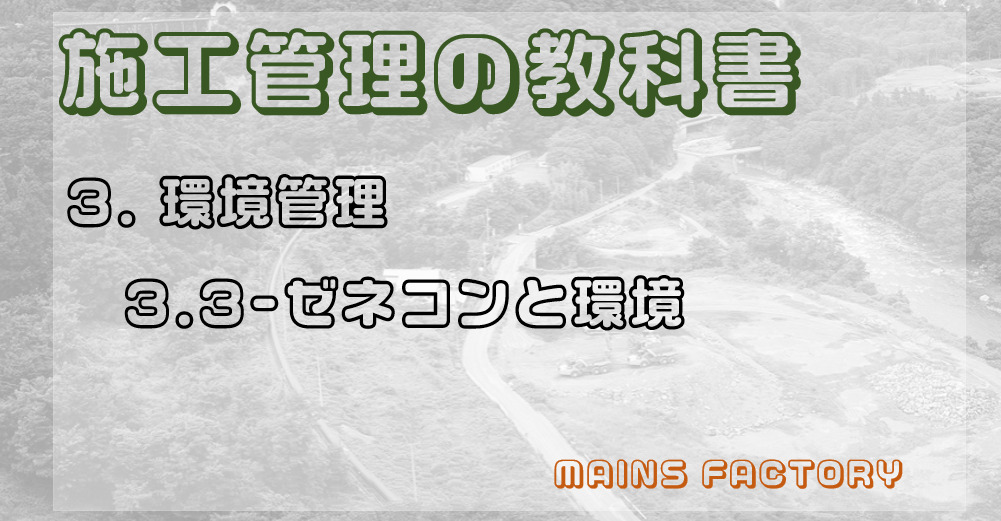


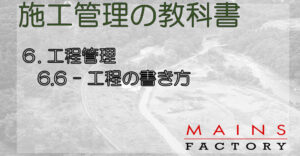
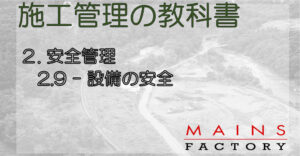
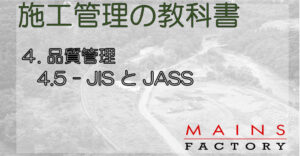

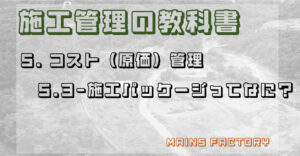
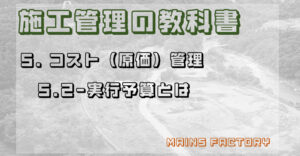
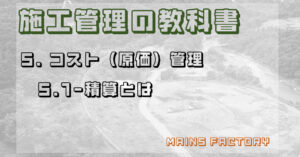
コメント