建設業の難関資格を合理的に取得するための極意を紹介していきます。
今から紹介する方法には、
資格取得の目的を「自己研鑽」と据えていて時間は「たっぷりある」という方には
あまりオススメできない方法もあるかもしれません。
しかし、資格取得に挑戦するには、受験費もかかりますし、やはり落ちるのはツライ。
だからより効率的に、できれば短時間で最大の成果を上げられることは、やはりいいことですよね。
それに非効率な方法で勉強しても遠回りになりますから効率的な勉強方法で長時間対策できることが最も合理的です。
決して楽して資格を取れる!という意味ではありませんのでご理解くださいね。
前置きが長くなりましたが、いかに効率的に資格を取得するか!を実現するたには共通するテクニックがあると思っています。
その1 過去問の徹底調査

最大にして最強のテクニックです。これ無くして合格の最短ルートは通れません。
「資格取得はあくまで付加価値で、知識取得が目的です。」
という方には必要のないことかもしれません。
学校の授業形式の勉強に慣れている人はこのステップを経ない人が非常に多くおられます。
要は教科書を1ページ目からしっかり覚えないと気が済まない人たちのことです。
ここで言いたいのは単なる調査ではなく、徹底調査の「徹底」が肝になることを強くお伝えしたいのです。
仮に過去問を先に見たとしても
「なるほどこんな問題がでるのか」という認識を持つ程度の方が多いのではないでしょうか?
それからじっくり勉強・・・
時間がある方はそれでもいいですが、時間がない・あるいは効率的に短時間で効果を出したい方に必要になってくるのが以下のステップです。
➊出題傾向を掴む、明確に理解する
➋問題文ではなく、問題の意図を理解する
➌回答の共通点・テクニックを理解する
➍思考停止してもいいところを理解する
です。順に説明します。
➊出題傾向を掴む、明確に理解する
どのような問題がどの程度の頻度で出されているのか。
これができると、最悪、勉強時間が足りない場合には、出題頻度が低い問題の勉強を捨てることが可能となり、頻出問題にはより多くの時間を使えます。
参考書を最初から丁寧に読み込むことが勉強と思われる方も多いと思います。
しかし試験には、必ず傾向や出題頻度(重み)があります。
参考書の多くには最初の方に、過去数年分の分類別の出題履歴が書かれています。
コンクリート技士だと施工系の問題が頻出しているが、主任技士だったら材料系が毎年絶対出題されている…などです。
これにより勉強がずっと楽になります。
また、親切に色々なことを書いてくれているサイトも多くあります。
技術士試験を目指す方なら絶対に知っておくべき
SUKIYAKI塾https://www.pejp.net/pe/
はいわゆる神サイトです。
(傾向だけではなく対策まで記されている!超優しい!私も今後このブログ内で書きます!)
絶対に出題されること・多分出題されること・多分出題されないこと・絶対出題されないことを同じ力を込めて勉強してはダメなのです。
頭でわかっていても、参考書を読み飛ばすのは怖い気持ちもあると思います。
でも出題には傾向があることを明確に理解しておいてください。
➋問題文ではなく、問題の意図を理解する
意味を少し掘り下げて考えます。
問題文とは「〇〇について回答せよ」の〇〇を指しますが、
例えば以下の設問では同じ〇〇でも答え方が変わります。
(1)高齢化社会・人口減少下での生産性向上を図る方法を述べよ
(2)人工知能(AI)を駆使した生産性向上を図る方法を述べよ
同じ生産性向上を図る方法を述べよ。でも前述する内容が異なり、
生産性向上についてではなく
(1)は高齢化社会・人口減少下
(2)は人工知能(AI)
についての知識が必要になってくることがわかりますでしょうか?
これらの問題をジャンルで分けると【生産性の向上】に間違いありません。
しかし問題の意図としては全く異なるものなのです。
…だがしかし!
私の短時間勉強法ではここからがテクニックで
高齢化社会・人口減少下での生産性向上にはAIが必要だし、
AIを駆使する生産性向上は高齢者社会・人口減少が問題となっているから…なのです。
わかりますか?
論文形式であれば、経緯を理解していることでよりわかりやすい回答をすることができます。
上記の場合の勉強方法は
【問題点】高齢化社会・人口減少
【解決方法】人工知能を駆使した生産性向上
という関係になります。
問題文だけに注視して勉強をする人と、問題の意図を理解して勉強する
さらに言えば回答を行う人では深みが変わってきます。
設問者がなぜ・どのような経緯がありその問題をしたのか?
論文でない場合にも、その問題をしたということはどういった要点を理解しておいてほしいからなのか?
を理解していれば、いい答えができると思います。
➌回答の共通点・テクニックを理解する
この項目は技術士試験編で詳しく説明しますが、主に論文対策で使えるテクニックです。
論文では
・問題(課題)と解決方法のつながり
・解決方法と現実(現状)のつながり
・思考の経緯
などを踏まえて記載することになると思います。
まずは問題文に対し、現状の説明、解決方法を記載するとしましょう。
解決方法にはあらゆる方法が考えられますが
例えば…
【問題】生産性向上を図るには
【現状】少子高齢化・働き手不足
【解決方法】業務の効率化
のストーリーが考えられます。次に
【問題】構造物の老朽化対策
【現状】点検対象が多く、点検に時間がかかり、対策を講じることができていない
【解決方法】業務の効率化
というストーリーが考えられます。
つまり異なる問題(課題)に対し同じ解決方法が使用できることもあるのです。
一つの問題に複数の回答を用意する。
技術士問題では一般的に複数の解決策を述べることが必要ですが
この方法を用いれば解決策の勉強は、問題数×3ではなくなります。
少し気が楽になりますよね。
自分の中で「この解決策はこの問題にも使えるぞ!」と
逆転の発想で関連性を持たせることも時に重要で、そういったことで対策時間を削減できると思います。
どんどん前向きに回答の共通点・テクニックを磨いてみてはどうでしょうか?
➍思考停止してもいいところを理解する
試験の中には、「そこはそれほどこだわらなくていいところ」というのがあります。
例えば技術士二次試験の筆記論文では1つの設問に複数の問題があり、
それぞれに回答します。
例えば
1.はじめに
2.多面的な観点からの課題抽出と内容
2.1 〇〇(課題)
2.2 △△(課題)
2.3 □□(課題)
3.最も重要と考える課題と解決策
〇〇・△△・□□のうち最も重要と考えられる課題を選んだ理由
3.1 ●●(解決策)
3.2 ▲▲(解決策)
3.3 ■■(解決策)
4. 新たに生じうるリスクと対策
リスク1:☆☆
対策 :★★
リスク2:▽▽
対策 :▼▼
5.業務として遂行するに当たり必要となる要件
技術者倫理…
持続可能性…
以上、羅列しましたが、
この内容はある意味フォーマットと捉えて問題ありません。
空欄の原稿用紙に上記は必ず書く内容です。
ここにテクニックは不要。つまり時間を使う意味はありません。
これだけで少なくても18行の記載が必要になります。
原稿用紙3枚であれば1/3が題名と項目番号です。
これだけ自動的に思考停止しても書けるのであれば気が楽になりますよね。
逆に変に項目番号は1がいいか?①がいいか?
など必要のないところに気を遣わないようにしてください。
無駄を省き、必要なところに必要な時間を使いましょう!

その2 勉強時間を分散する
「勉強時間の分散」の逆を言うと「一夜漬け」です。
一夜漬けがどれだけ記憶に残らないかは皆さんも重々わかっていると思います。
学生時代の限られた範囲内を覚えるだけでできたテストと
これから皆様が受験しようとしているテストの絶対的違いは
「暗記では合格できない」ところにあります。
記憶力・思考力を最大限に働かせるには、
・知識の吸収
・脳への定着
・発想の積重ね
が大事です。
知識は参考書や過去問等から仕入れますが
脳に定着させるには時に繰り返しの復習や失敗が定着させることにつながります。
そして自分の頭でかみ砕いて発展性を持つ、その中で疑問点が生まれればより良いでしょう。
疑問に思う、時にこれは違うんじゃないか?
と自分の意思を持つことができればもう自分の能力と言っていいです。
そうやって勉強は一度にまとめるのではなく、繰り返しの中で知識は深まります。
例えば、一日で2時間勉強しようと思っていれば2時間まとめて行うより
30分×4回の方が効率的です。
睡眠が知識を定着させるという話を聞いたことありますよね?
同じように空白時間が頭に定着させてくれます。
30分の最初の5分を前回の復習に充てていればどんどん深い知識取得になります。
さらにその空白時間で実は頭の中で知識がグルグル回っていて
「あれ?あの内容実はよくわかってなかったぞ」とか
「あの時勉強したアレとさっき勉強したコレに関連があるのでは?」など
思考が深まっていくからです。
勉強していない時間を「仮想勉強」の時間にするために
勉強時間は分割配置することがオススメです。
その3 なるべく文字を書かない
多くの試験が論文や筆記問題で文字を書くシーンが多いのになぜ文字を書かない方がいいのか?
これはあくまで『本当に』時間がない人の場合です。
ただ文字をかかないのではなく、思考の中で文章は作成します。
「流れ」を身体に染み込ませるのです。
これには理由がいくつかあります。
・過去問や想定問題と同じ問題は出ないこと
・文字を書くのは時間がかかること
・文字を書くことに満足してしまうこと
です。
過去問や想定問題と同じ問題は出ないこと
わかっていると思いますが、文章を書くことに精を出すと、一言一句に拘り小さなことに気が付くようになります。
それ自体はいいことなのですが
全く同じ問題がでないのに、その問題に対する時間を使いすぎると、時間がない中での試験勉強では有効な時間利用ができません。
だから問題数をこなし、思考の訓練に充てた方が良いのです。
1問にかける時間が圧倒的に変わってきます。
思考の訓練にかけた時間はハプニングやイレギュラーな問題にも対応できるようになります。
オーソドックスな問題に時間をかけるより、必ず想定外が発生する試験においては、思考の訓練時間が勝敗を分けるのです。
文字を書くのは時間がかかること
先述したものとほぼ同じですが、
書く時間に対し、考える、もしくは喋る時間では圧倒的に書く時間は、長くなります。
試験には時間がありません。
必ず、最初の数分で思想(方向性)を決めて、時間いっぱいで書き切る必要があります。
思想(方向性)の訓練でいかに早く・正確にゴールを見出さないと十分な筆記時間を確保できなくなります。
書きながら考える・書かないと思いつかない人はよりこの練習を行うべきなのです。
ただし、文字は書かないが、フロー図や思考のイメージを図化する作業は行っておくべきです。
最初の思想から筆記中にブレを無くすためです。
文字は書かず、メモ・図・フローなどで論文の全容を表わす訓練は有意義です。
文字を書くことに満足してしまうこと
私がまさにそれなのですが
文字をたくさん書いたノートを見ると充実感に浸り満足します。
「たくさん勉強したなぁ」 「今日はこれくらいでいいか」
なんてこともしょっちゅう。
でも実際の情報量で言うと
参考書はほとんど進んでいなかったり、たった1問の問題を解いたくらいのことが多いと思います。
500ページの参考書があって、1日2ページ勉強していたら250日かかります。
250日あればいいですが仮に250日あっても最初のころの勉強は忘れているでしょう。
ですからその何倍ものスピードで情報を蓄積し、何度も繰り返し同じものを読む・見る方が
ずっと情報の上書きがなされ、様々な情報とリンクし、知識が深まります。
文字を書いて勉強した気になってはいけません。
簡単ですが最も陥りやすい病気です。
やった気にならず、本当にやる。それが、結果がすべての試験勉強なのです。

その4 他者からの「迷いの根源」を徹底排除
ある試験を
・10年前に合格した非常に親切に教えてくれる人
・昨年合格したあまり教えてくれない人
がいた場合、親切に教えてくれる人から指導をしてもらうでしょう。
同じようにネットの情報でも10年前の情報は世に溢れています。
でもその10年の間に出題傾向は大きく変わり、必要な資質も変更されているかもしれません。
つまりゴールがブレているのです。
そうなるとどれほど親切に指導してくれても意味がない(と言ったら怒られるけど)のです。
ネットでも同じです。
それを判断するのは下調べの量と自分の意思です。
まず自分が受験する際の、必要な資質や出題内容を知る。
これは試験の概要に必ず記載しています。
そして教えてくれている情報が正しいのか(古くないか)を自分の意思で判断するのです。
間違った情報をひたすら信じ続ける方が、自分で勉強するより不利になることもあります。
他者からの「迷いの根源」を排除し、正しい情報を仕入れてください。
より正しいと思われるのはやはり最近合格(受験)した人の指導や知識です。
自分の本当に必要とする情報をシンプルに仕入れ、情報過多で迷いが発生しないよう
自分の芯を持って取り組んでいただきたいと思います。
その5 出題想定を極める
ここまでテクニック面の話をたくさんしてきましたがあとは量をこなすだけ。
量のこなし方は先述した通り、一つの問題を熟考するのではなくいかに多くの想定される出題内容を考え出し、
出題内容に対する答えを持っておくか。が大事です。
出題内容も例えば
「環境問題」として環境問題に対する知識を深めるより
「環境問題の現状」
「環境問題の解決方法」
さらには
「土木業界における環境問題」
「日本における環境問題」
など同じ「環境問題」でもたくさんの出題内容が想定されます。
ただ単に「環境問題」に対し3つほど答えを持っておけばいいか
と思っていると
「環境問題の解決方法」
との出題に自分の回答案が1つも当てはまらない可能性があります。
そうなると試験中は地獄の時間です。
でも様々な「環境問題」の出題について3つずつの答えがあれば
ただ単に「環境問題」について述べよと言われても多くの中から最も適した内容での記述ができます。
出題想定を自分で想定し、いかに多くの回答を用意しておくかが大事ということがわかると思います。
出題文だけでパニックにならないように事前の準備は必要です。
自分で問題を作りだすのはいくらでもできます。
でも知識習得だけで時間を使い切ってしまうと想定する時間がなくなります。
だからここまでの域に達するまでの時間は必要最低限にし、いかにこのレベルの対策に時間を使えるかが大事なのです。

最後に
長くなりましたが
一連の試験テクニックを書きました。
この考え方は全ての試験に通ずるところがあると思います。
有限の時間の中で、かつ日常業務に追われながらの試験勉強で
いかに最小の時間で最大の成果を出せるか
そのことを勉強の開始時点で考えながら、
合格のために本当に必要なことを徹底して実践してほしいと思います。

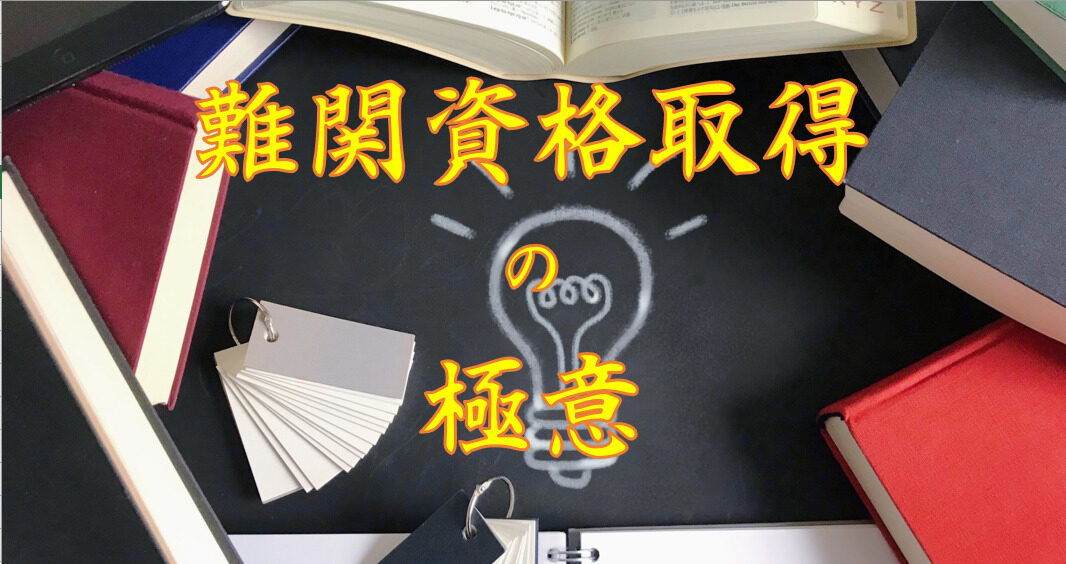


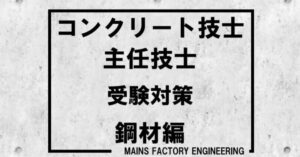
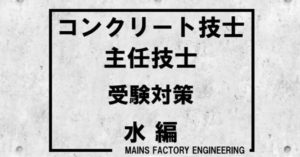
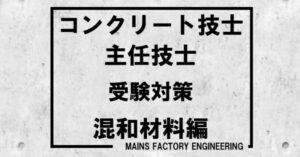
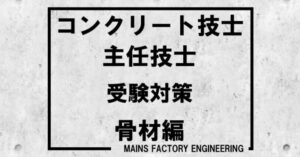

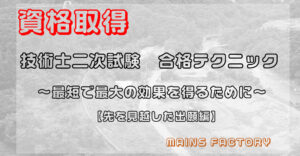

コメント