安全に関わる法律
建設業において安全と関係のある法律は以下のものがあります
・建設業法
・労働安全衛生法
・労災保険法
・労働基準法 等
この中でも『労働安全衛生法』『労災保険法』が現場運営の中では強く関わってきます。
さらに、現場の施工管理の面では『労働安全衛生法』を知ることが非常に重要です。

労働安全衛生法とは
こういった法律ではその法律の意味を,法令の冒頭に記載してあります。
こちらの法律も同じですので最初の項を一部引用いたします。
「この法律は労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場勘定の形成を促進することを目的とする。」
例のごとく非常に難しい言い回しなので簡単に言いますと
快適職場(安全に充実した仕事ができる職場)を形成するために
・責任の明確化
・自主的活動の促進の措置を講ずる
ことを主目的としているわけです。
責任の明確化
この言葉は非常に労働安全衛生法を端的にまとめていたわかりやすい言葉だと思います。
労働安全衛生法(以下:安衛法)を見たことがある人はわかると思いますが、安衛法は必ず冒頭に『誰が』この法律を守る必要があるのかを記載しています。
例えば
第二章
労働災害防止計画(労働災害防止計画の策定)
第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聞いて…
第三章
安全衛生管理体制(統括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業所ごとに…
のように『〇〇が』という風に誰がその法律を守るのかについて明確化されています。
これらは法律ですのでつまり『誰がそれを破れば罰せられるのか』を記載しているとも言い換えられます。
名称の説明
ここで知っておくべき名称の代表のみお伝えしておきます。
厚生労働大臣
そのまま。
都道府県労働局長
上記同様。
事業者
事業を行う者で、労働者を使用するもの。より現実に近くいいますと、作業員を雇う会社、多くの場合が下請けの会社そのものをいいます。(元請けで作業に従事する場合や、元請け社員に対しての場合は元請けが事業者にあたることもあります)
元方事業者
こちらが元請け会社を指します。
ほとんどが事業者
安衛法を見ているとほとんどが『事業者は』でスタートします。
事業者、つまり作業する人を雇っている会社は、作業する人を守る必要がある。
ということで、自社で自分の社員を守りましょう!ってことがほとんどの法律に示されているのです。
なんとなく下請けはモノを作る成果を挙げることが仕事で元請けはそれをうまくコントロールする(安全も含め)のが仕事だと思われがちですが、決してそんなことはなく、自社社員の安全は自社で自主的に守る必要があるということが示されています。
自主的活動の促進の措置を講ずるとは?
こちらの意図の解釈としては、安全に対してちゃんと意識を持ち作業をさせること、またそれらの基準などを設け具体的行動を促すこと、さらにそれらだけではなくより安全な働きやすい職場を構築すること。を指していると思われます。
安全の対策とは全ての状況に完全一致するようなものはありません。適宜その状況に応じて使い分けたり瞬時に対応したりする必要があります。
ですから安衛法のような非常に多い文字・頁を有する資料であっても全ての状況を網羅することはできません。よって、安全意識を向上させ、それらの対策を自主的に発揮できるようにしてください。統一した作業環境の中で最低限のルールだけは書いておきます。という認識だと思っています。
実際に法律と触れるシーン
起こってはいけないことですが、あなたの現場で事故(災害)が起こったとします。
その場合、どういった事象が発生するかにより説明していきたいと思います。
災害~現場検証~裁定
まず災害が起これば,被害者の救助とともに救急への連絡を行います。
体調が悪い時や作業に関係ない時はこれだけでよいですが,
現場での災害である場合には加えて,
自現場の所管である労働基準監督署に報告する必要があります。
正確には休業4日以上の災害である場合には報告義務がありますが,
その時の災害の大小によっては即時報告するべきです。
これは元方事業者が行うべきです。
その後,必要に応じて所轄警察に連絡することになります。
これは労働基準監督署が行う場合もあります。
災害の度合いによっては現場検証がなされます。
これは監督署のみの時もあれば警察が来ることもあります。
災害発生要因の特定を行うわけです。
ここで警察が来る場合は『事件性の有無』を確認するためです。
現場作業を装って故意に怪我をさせていないか?ということです。
事件性が無ければ警察は引き上げます。
監督署はその後,当日の作業にあたり必要な指示・指導がなされていたか?等を確認するため
書類を要求することが多いです。
そしてそれらの書類を持ち帰り,
必要に応じて重要参考人を監督署に呼び出し,質問を受けます。
さらにしばらくしてから今回の災害の裁定が行われます。
これが一連の災害が起こった場合の流れです。

警察からの罰・監督署からの罰
調査の中でまずは事件性の確認として警察が調査を行います。
もしこれに当たった場合には刑罰が下されます。こういう事例はあまりないでしょう。
次に労働基準監督署が調査し,どこに問題があったかを調査します。
設備に不備があり,それを確認していなかった場合には事業者が指導されますし,
作業指示や環境に問題があれば元方事業者が指導指導されます。
これらの指導事項はいわゆる指導票などと言われる書面をもって行われます。
指導票のほかにも様々なレベルの通知書があり
・是正勧告書(法令違反がある場合)
・指導票(法令違反までなくても法違反に繋がる恐れがある場合)
・使用停止等命令書(緊迫した危険があり,緊急を要する判断の場合)
があります。
臨検などで足場の隙間等が見られる場合には使用停止等命令書が出された。
なんてことがあります。
今回例にしている災害時の場合であれば,法令違反があれば是正勧告書,そうでなければ指導票が発行されます。
これらは統括安全衛生責任者や雇用主など代表者,もしくは作業を指示した担当者宛と会社宛に発行されることがあります。

どのような罰があるのか?
法律に触れているわけですから罰が付きまといます。
・罰金もしくは懲役が課せられる刑罰
・会社の営業停止などの行政罰
等があります。
法律の意義
建設業の法令は人を罰するためにあるのではなく冒頭に示した通り『自主的活動の促進の措置を講ずる』ことを目的としており,現場状況を自ら安全な状態に保ち,怪我・災害のない現場を創出することを目的としています。
そのための法令であり,これらの法律を最低限守ることは人命を守る上で非常に重要なものです。
法令を全て覚えることは不可能ですが,足場を組むのであれば最低限,足場の法律を確認しておくことが必要でしょうし,法律の観点で組立終わった後の確認をするべきです。
その手間がなく,災害が発生すればそれはあなたの責任になるかもしれません。
建設業の作業自体は法律と非常に密接に関わっていますが,決して作業性を損なう,いじわるなものではありません。人の命を守る最低限実施すべきものとして捉え,前向きに取り組んでもらいたいと思います。


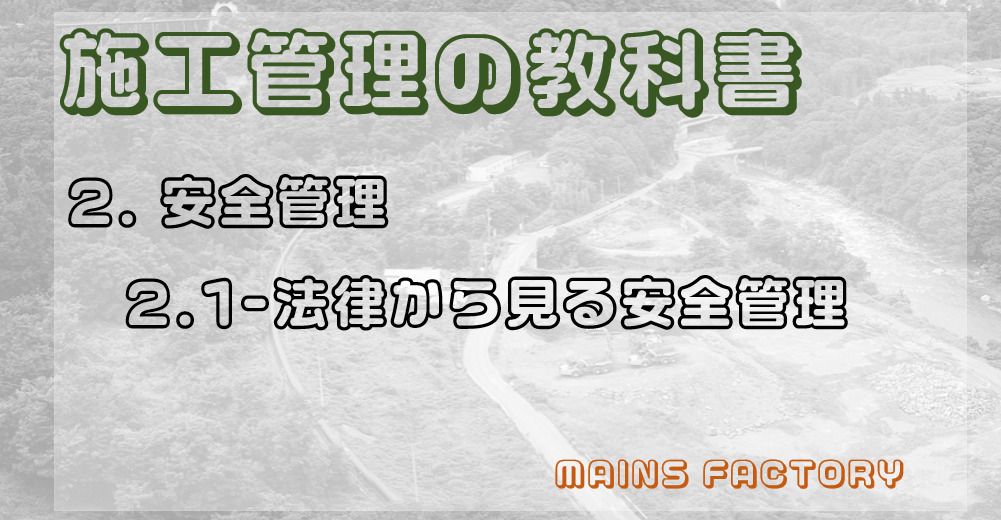


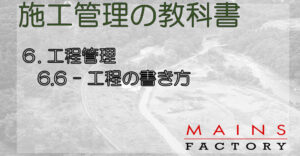
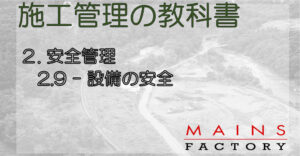
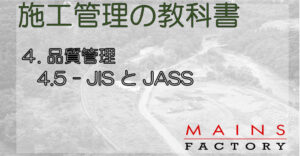

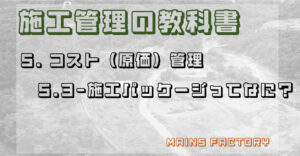
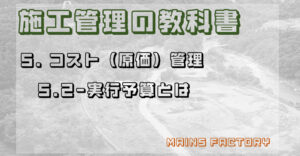
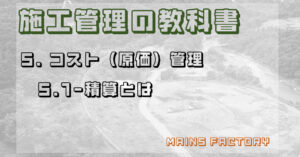
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 2-1.法律から見る安全管理 – MainsFactory […]