今回は実行予算について説明します。
前回,積算について説明いたしましたが,そちらを理解してからの方がわかりやすいと思いますので読まれてない方はそちらを先にお目通しください。
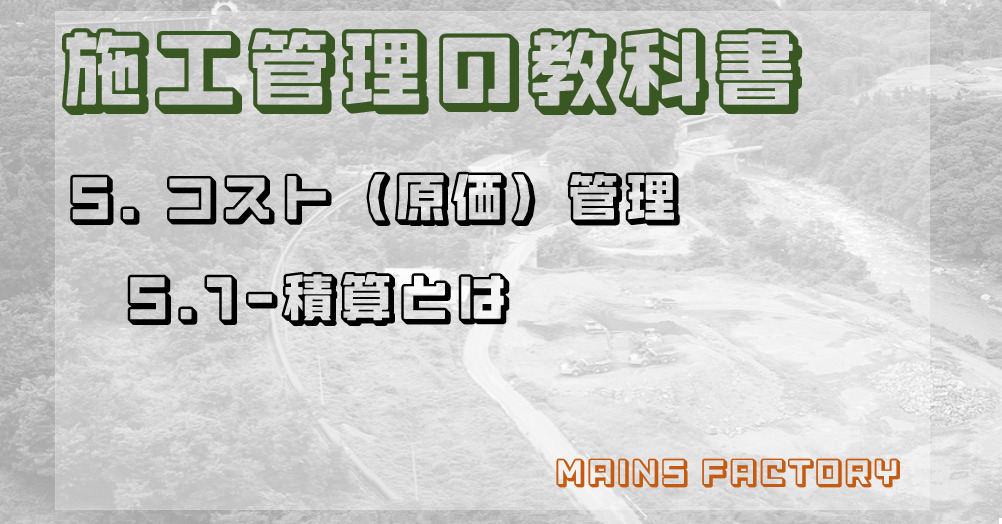
実行予算とは
実行予算とは文字の通り,現場で工事をするにあたり必要となる費用を積上げていき実行可能な予算を算定したものです。
積算は発注者の基準に基づいて工事金額を算定したものでルールに則ると基本はみんな同じ金額になるものでした。
見積は積算に対して利益を考慮した金額でありますが,入札時にはその利益を小さくして安く見積をする必要がありますが,設計変更等では積算に単純に利益を載せた見積にする等,場合によって金額が変わるものでした。
実行予算は,施工場所や方法・仕様,協力会社や自社の施工体制等,様々な要因によって大きく金額が変わるものです。順に説明していきます。
実行予算の意味
実行予算は本来,入札時に作成しておく必要があります。
多くの方が積算=標準的な施工を行えば,それ以下の金額で行えるもの。
と思っていると思いますが,決してそうとは限りません。
積算よりも高くかかりそうなところがあれば事前に把握しておき,逆に効率的に行うことで積算よりも安くできるところがあればそれが利益の部分になるのです。
実際にかかる費用を確認する行為が事項予算の意味ですから,
工事が始まればこの予算を基に『原価管理』を行います。
原価管理とは
原価管理とは先述した実行予算を基に管理するものですが,
実行予算は着手時に『予算』として管理するものですが原価管理は工事中に『収支管理』するものですから,
常に収支と予算の比較が必要になります。
想定していたよりも工事が長引いてしまったり,
何らかのミスでやり直しが発生したり,
はたまた降雨により工事が中止したり,
材料が余ったりすると,予算より余分にお金がかかることになります。
これらのお金がかかりすぎると『赤字』になるわけです。
実行予算と積算が違う代表例
ここでは実行予算が積算を上回ったり異なったりする例を紹介します。
◆非常に難しい施工状況の場合
国交省の積算では施工パッケージもしくは国交省の標準積算を用いて行いますが,
施工規模によって積算よりも実際の方が,費用が多くかかる場合があります。
例えば,施工パッケージ『土工事・掘削』の場合
『施工方法』の選定では
「オープンカット」
「片切掘削」
「水中掘削」
「現場制約あり」
「上記以外(小規模)」
とあります。
ここで1m3だけを掘削する試掘工事であった場合,選択は「上記以外(小規模)」になります。
さらにその先の『施工数量』の選定では
「小規模(標準)」
「小規模(標準以外)」
があります。
(標準)は100m3以下を示し(標準以外)は50m3以下を示します。
1m3なので「小規模(標準以外)」を選択します。
そうすると・小型バックホウ・運転手(特殊)の配置で1mあたり2,300円程度のお金が積みあがります。
さて実際は試掘なので,手掘りを考慮して,
職長(土木一般世話役)・普通作業員2名の配置で行ったとしましょう。
単純に1日で7万円程度のお金がかかりますから
70,000 – 2,300 = 67,700円の赤字となります。
◆使用する単価が異なる場合
積算には積算基準日というものがあり,「このタイミングの単価を用いて積算してください」というのが決められます。
労務単価であれば毎年2月頃に来年度の新規単価が公表されますし,
建設物価では毎月新単価が公表されています。
多くの場合に,新年度になりますと単価の改定が行われ,
近年の働き方改革や世界情勢的に物価は高くなる一方です。
そうすると工事の入手時と実際にモノを買ったり,
人に作業をしてもらったりする時の値段に乖離があることが多くあります。
純粋に必要な数量は変わりませんからほぼ間違いなく赤字になります。
業界的にはいわゆる「持ち出し」と言われる状態で工事をすることになります。
これらの救済措置として『スライド』というものがありますが,ある一定の値上がり幅がなければ清算できない場合もあります。
◆数量や仕様が異なる場合
積算は設計図書に基づいて行うものですが施工自体は現地の形状や状況に合わせて造ることも多くあります。いわゆる現地合わせというものです。
この現地合わせは予めわかっていたものか,予期しなかったものかで取り扱いが異なります。
わかっていたものであれば積算時点でそれを踏まえておくべきですし,
予期しなかったものは,説明がつく場合には「設計変更」して費用を請求する必要があります。
当然,数量や仕様が変わればかかった分は頂戴しないといけませんよね。
もちろん減額になることもありますが,設計図書と造ったものが異なるのは大きな問題です。
これらは現場を管理する上では常に行っておく必要があり,
設計図書に定められるものを適正に造るのがゼネコンの仕事ですが,
時として現地合わせが根拠のないものになり,
余分にお金がかかっているが把握できていないこともあります。
こういったことがないように数量や仕様の把握は非常に重要になります。
設計変更については別の機会で詳しく説明することにします。
実行予算の注意事項
先述した通り,実際の積算よりも高くなったりする可能性は大いにあるので,実行予算を掴んでいないで,積算の通りに入札すると赤字で工事を入手することがあるのです。
この場合には,入札時に予め条件を整理して高くなる要素を見込んでおく必要があります。逆に利益がでそうなところと差し引きし,トータルで利益が出そうであればそのまま工事入手することもあるでしょうし,そこは駆け引きと言いますか,方針によると思います。
実行予算の内容
予算の構成は以下のようなものになります。
『工事原価』+『経費』
工事原価は直接工事費と共通仮設費に分かれます。
直接工事費はお分かりの通りモノを造るためにかかる人・モノ・機械等に必要なお金です。
共通仮設費は
大型機械の組立解体費や資材の運搬費,
仮設道路や仮設の水道・電気代,安全設備費,
あるいは周辺へのイメージアップのための費用など,
工事に影響を及ぼすような仮設費用になります。
経費は工事経費と一般経費に分かれます。
工事経費は現場事務所として必要な運営費用であり
一般経費は会社の本支店などの運営費用になります。
このように実は予算の中身は多く内容を含んでいるため,
現場作業ができたから間違いなく利益があるんだ!というわけにはいきません。
工事自体に予算があり,必要経費を踏まえて計算するので,
まるで一つの会社を運営するような感じですよね。
国交省の請負工事費の構成とほぼ同じ分類で管理します。
国交省の積算では直接工事費と共通仮設費の積み上げ分以外は率計上となっています。
ここらへんの詳しくは改めてご説明しますね。

まとめ
実行予算は現場運営する上で非常に重要なものです。
成り立ちを理解し,日ごろの業務の積み重ねが重要ですから,おろそかにしていますといつの間にか大赤字現場になる可能性もあります。ただお金の部分を理解している現場管理は非常に重宝されますし,一味違った現場管理ができます。ですからぜひとも理解してもらいたいと思います。
わからないことはぜひMAINSFACTORYまでお問合せください!
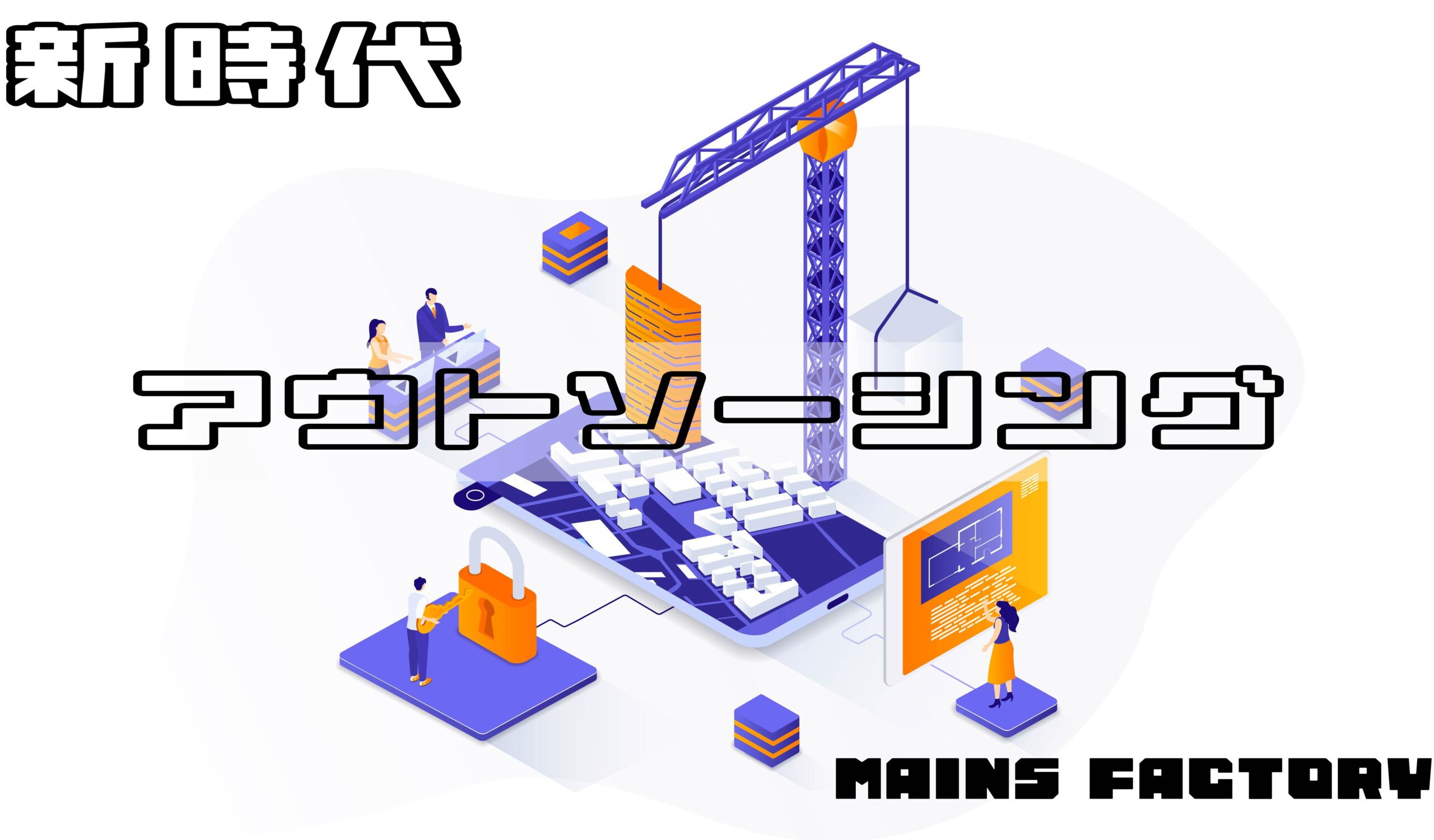

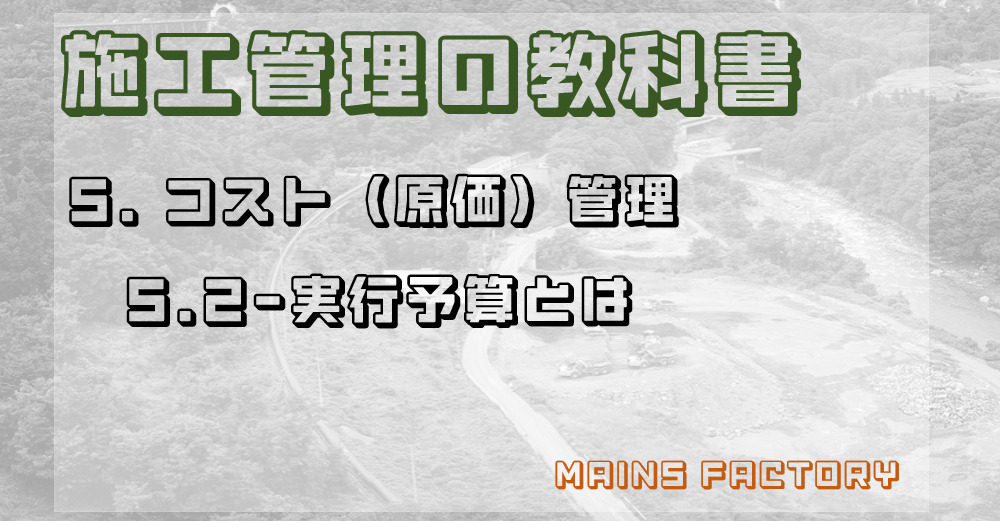


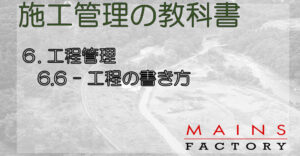
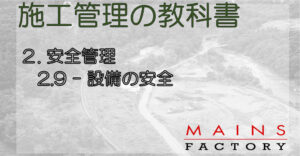
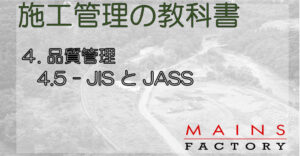

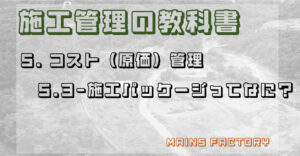
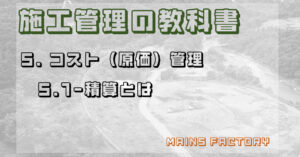

コメント